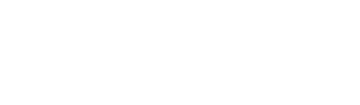税理士なんでも相談室
法人のお客様
法人税務顧問
HOME >
税理士なんでも相談室
> 税理士なんでも相談室
平成27年度税制改正はどのようなものですか?
(1)法人税率の引き下げ
法人税の税率を23.9%に引き下げ
(2)欠損金の繰越控除制度の見直し
大法人の控除限度額を65%・50%に引き下げ、繰越期間を10年に延長
(3)雇用者給与支給額が増加した場合の税額控除制度の要件の緩和
給与等の増加割合要件を3%(大法人は4%)以上増に緩和
(4)受取配当等の益金不算入制度の見直し
保有割合が1/3超の場合は100%を、1/3以下の場合は50%を、5%以下の場合は20%を益金不算入
(5)中小法人の貸倒引当金に係る簡便法の基準年度の見直し
基準年度を平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した事業年度に変更
(6)研究開発税制の見直し
控除限度額を法人税額の25%(総額型)とし、特別試験研究費に係る控除限度額を別枠で法人税額の5% (オープンイノベーション型)とする
(7)地方拠点強化税制の新設
本社機能を東京圏から地方に移転した場合等における特別償却・税額控除及び雇用促進税制の拡充
(8)法人事業税の外形標準課税の拡大
付加価値割及び資本割の標準税率を2倍に引き上げ
法人税の税率を23.9%に引き下げ
(2)欠損金の繰越控除制度の見直し
大法人の控除限度額を65%・50%に引き下げ、繰越期間を10年に延長
(3)雇用者給与支給額が増加した場合の税額控除制度の要件の緩和
給与等の増加割合要件を3%(大法人は4%)以上増に緩和
(4)受取配当等の益金不算入制度の見直し
保有割合が1/3超の場合は100%を、1/3以下の場合は50%を、5%以下の場合は20%を益金不算入
(5)中小法人の貸倒引当金に係る簡便法の基準年度の見直し
基準年度を平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した事業年度に変更
(6)研究開発税制の見直し
控除限度額を法人税額の25%(総額型)とし、特別試験研究費に係る控除限度額を別枠で法人税額の5% (オープンイノベーション型)とする
(7)地方拠点強化税制の新設
本社機能を東京圏から地方に移転した場合等における特別償却・税額控除及び雇用促進税制の拡充
(8)法人事業税の外形標準課税の拡大
付加価値割及び資本割の標準税率を2倍に引き上げ
平成26年度税制改正はどのようなものですか?
(1)生産性向上設備投資促進税制の創設
特定生産性向上設備等の50%特別償却
(2)中小企業投資促進税制の拡充と延長、
一定の特定生産工場設備等の即時償却
(3)研究開発税制の拡充と延長
試験研究費の増加額の30%税額控除
(4)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例の延長
30万円未満即時償却の2年間延長
(5)所得拡大促進税制の適用要件緩和と延長
(6)復興特別法人税の1年前倒し廃止
(7)交際費課税制度の見直し
(8)ベンチャー投資促進税制の創設
(9)事業再編促進税制の創設
(10)耐震改修投資促進税制の創設
(11)国家戦略特別区域法の制定に伴う措置
(12)創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置の創設
(13)地方法人税(国税)の創設
特定生産性向上設備等の50%特別償却
(2)中小企業投資促進税制の拡充と延長、
一定の特定生産工場設備等の即時償却
(3)研究開発税制の拡充と延長
試験研究費の増加額の30%税額控除
(4)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例の延長
30万円未満即時償却の2年間延長
(5)所得拡大促進税制の適用要件緩和と延長
(6)復興特別法人税の1年前倒し廃止
(7)交際費課税制度の見直し
(8)ベンチャー投資促進税制の創設
(9)事業再編促進税制の創設
(10)耐震改修投資促進税制の創設
(11)国家戦略特別区域法の制定に伴う措置
(12)創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置の創設
(13)地方法人税(国税)の創設
消費税の平成27年度改正はどのようなものですか?
(1)消費税率10%への引上の時期
平成29年4月1日とされました。
(2)国境を越えた役務提供に対する消費税の課税の見直し
国外事業者が行う電子書籍や音楽・広告の配信を国内取引として課税対象に
(3)外国人旅行者向け免税手続き
商店街等の店舗ごとの免税手続きを一括して行うことができる
平成29年4月1日とされました。
(2)国境を越えた役務提供に対する消費税の課税の見直し
国外事業者が行う電子書籍や音楽・広告の配信を国内取引として課税対象に
(3)外国人旅行者向け免税手続き
商店街等の店舗ごとの免税手続きを一括して行うことができる
消費税の改正点(平成23年9月)はどのようなものですか?
(1)事業免税点の判定
【個人業者】
個人事業者は、その年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合であっても、
特定期間(その年の前年1月1日から6月30日までの期間)における課税売上高が1,000万円を超えるときは、課税事業者となる。
(注) 特定期間中に支払った給与などの金額の合計額をもって、特定期間における課税売上高とすることができる。
【法人】
法人は、その事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合であっても、
特定期間(その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間)における課税売上高が1,000万円を超えるときは、課税事業者となる。
(注) 特定期間中に支払った給与などの金額の合計額をもって、特定期間における課税売上高とすることができる。
(2)95%ルールの見直し
課税売上割合が95%以上であっても、その課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、
課税仕入れなどの税額の全額を仕入控除税額として売上げの消費税額から控除すること(全額控除)はできないこととされた。
【個人業者】
個人事業者は、その年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合であっても、
特定期間(その年の前年1月1日から6月30日までの期間)における課税売上高が1,000万円を超えるときは、課税事業者となる。
(注) 特定期間中に支払った給与などの金額の合計額をもって、特定期間における課税売上高とすることができる。
【法人】
法人は、その事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合であっても、
特定期間(その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間)における課税売上高が1,000万円を超えるときは、課税事業者となる。
(注) 特定期間中に支払った給与などの金額の合計額をもって、特定期間における課税売上高とすることができる。
(2)95%ルールの見直し
課税売上割合が95%以上であっても、その課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、
課税仕入れなどの税額の全額を仕入控除税額として売上げの消費税額から控除すること(全額控除)はできないこととされた。
社葬費用は損金になりますか?
法人が、その役員または使用人が死亡したために社葬をおこない、その費用を負担した場合において、
その社葬をおこなうことが死亡した役員などの地位、会社に対する功績などを総合勘案して、相当と認められるものであり、
かつ、その負担した費用が社葬のために通常要するものであると認められるときは、その支出をした日の属する
事業年度の損金の額に算入することができます。
社葬のために通常要する費用とは、通常は、会葬のための費用をいい、遺族が個人的に負担すべき密葬の費用、
墓石及び墓地の購入費、戒名料、法会に要する費用などはこれには含まれません。
また、会葬者の持参した香典などを遺族の収入とした場合には、法人の収入としないことができます。
その社葬をおこなうことが死亡した役員などの地位、会社に対する功績などを総合勘案して、相当と認められるものであり、
かつ、その負担した費用が社葬のために通常要するものであると認められるときは、その支出をした日の属する
事業年度の損金の額に算入することができます。
社葬のために通常要する費用とは、通常は、会葬のための費用をいい、遺族が個人的に負担すべき密葬の費用、
墓石及び墓地の購入費、戒名料、法会に要する費用などはこれには含まれません。
また、会葬者の持参した香典などを遺族の収入とした場合には、法人の収入としないことができます。
信用保証協会に支払う保証料はどのように経理しますか?
(1)前払費用として経理する方法
前年に繰上完済したとした場合に返済を受ける保証料の額と
本年に繰上完済した場合に返済を受ける保証料との差額を本年の必要経費に算入する。
(2)繰延資産として経理する方法
保証料として支払った金額を、その保障期間(融資を受けている機関)に応じて償却をおこない
その償却費を各年の必要経費に算入する。
前年に繰上完済したとした場合に返済を受ける保証料の額と
本年に繰上完済した場合に返済を受ける保証料との差額を本年の必要経費に算入する。
(2)繰延資産として経理する方法
保証料として支払った金額を、その保障期間(融資を受けている機関)に応じて償却をおこない
その償却費を各年の必要経費に算入する。
-
会社設立
医療法人の設立はどうするのですか?
基金拠出型法人が設立しやすいです。平成19年以降持分なしの医療法人しか設立できません。
基金拠出型医療法人とは、定款上に基金制度についての定めがある、持分の定めのない社団医療法人です。
基金とは、拠出された金銭その他の財産です。「基金」はその拠出者に対して数年後返還されます。
基金拠出型医療法人とは、定款上に基金制度についての定めがある、持分の定めのない社団医療法人です。
基金とは、拠出された金銭その他の財産です。「基金」はその拠出者に対して数年後返還されます。
登記関係はできますか?
提携先の司法書士に依頼します。設立登記費用は約30万円で、1週間位で完了します。建設業の許可申請なども行政書士がおります。
個人のお客様
個人税務顧問
賃貸用建物の譲渡と課税事業者
個人で不動産の賃貸業を営む方(免税事業者)が、たまたま前々年の平成26年(本年、平成28年)、いわゆる基準期間に賃貸用建物を1千万円超(税込)で譲渡していた場合、本年、平成28年は課税事業者になって、仮に、本年中に貸店舗等の賃貸収入などがあれば消費税の納税義務が生じることになります。
●免税事業者にとっては予測し難い
というのも、個人で小規模又は居住用不動産の賃貸業を営んでいる方は、譲渡年(前々年)においても、多くの場合は免税事業者ですから消費税の納税義務は生じません。また、事業者の方自身が課税か免税かを特段意識されていないこともあってか、譲渡をした年の翌々年の状況を気に留めることはまずないように思われます。
このようなケースで、平成28年に再度、別の賃貸用建物を譲渡してしまうこともあります。この状況に至っては、災難ともいえる酷な状況を招来させます。建物の譲渡価額が5千万円であれば、単純に見積もって、消費税額の負担は400万円相当です。
消費税負担額の予測可能性を認識するには、少なくとも、前々年の譲渡時に税の専門家の関与が不可欠かと思われます。
●簡易課税の選択と課税期間の短縮
平成27年中に簡易課税選択の届出を失念、そして、本年の売買契約締結後引渡前の段階で、どのような税負担軽減の対策が講じられるかですが、以下が限界のように思われます。もっとも、前々年の課税売上高5,000万円(税込)以下が前提です。
①3か月間の課税期間の短縮と簡易課税選択の届出書の提出、②3か月間の課税期間の短縮の届出が間に合わなければ、1か月間の課税期間の短縮と簡易課税選択の届出書の提出です。
もちろん、これら課税期間の短縮と簡易課税を選択するとその適用が2年間継続することになりますが、建物譲渡に伴う課税期間の消費税の負担を軽減できれば、免税事業者にあっては、その後の課税期間は非課税売上が圧倒的に多く、課税売上があっても僅かですので大きな事務負担になることはないように思います。
ちなみに、賃貸用建物の譲渡に伴う簡易課税のみなし仕入れ率は40%ではなく60%です。少なくとも、消費税の負担を相当軽減できます。
●免税事業者にとっては予測し難い
というのも、個人で小規模又は居住用不動産の賃貸業を営んでいる方は、譲渡年(前々年)においても、多くの場合は免税事業者ですから消費税の納税義務は生じません。また、事業者の方自身が課税か免税かを特段意識されていないこともあってか、譲渡をした年の翌々年の状況を気に留めることはまずないように思われます。
このようなケースで、平成28年に再度、別の賃貸用建物を譲渡してしまうこともあります。この状況に至っては、災難ともいえる酷な状況を招来させます。建物の譲渡価額が5千万円であれば、単純に見積もって、消費税額の負担は400万円相当です。
消費税負担額の予測可能性を認識するには、少なくとも、前々年の譲渡時に税の専門家の関与が不可欠かと思われます。
●簡易課税の選択と課税期間の短縮
平成27年中に簡易課税選択の届出を失念、そして、本年の売買契約締結後引渡前の段階で、どのような税負担軽減の対策が講じられるかですが、以下が限界のように思われます。もっとも、前々年の課税売上高5,000万円(税込)以下が前提です。
①3か月間の課税期間の短縮と簡易課税選択の届出書の提出、②3か月間の課税期間の短縮の届出が間に合わなければ、1か月間の課税期間の短縮と簡易課税選択の届出書の提出です。
もちろん、これら課税期間の短縮と簡易課税を選択するとその適用が2年間継続することになりますが、建物譲渡に伴う課税期間の消費税の負担を軽減できれば、免税事業者にあっては、その後の課税期間は非課税売上が圧倒的に多く、課税売上があっても僅かですので大きな事務負担になることはないように思います。
ちなみに、賃貸用建物の譲渡に伴う簡易課税のみなし仕入れ率は40%ではなく60%です。少なくとも、消費税の負担を相当軽減できます。
平成27年度税制改正(所得税)はどのようなものですか?
(1)ジュニアNISA制度の新設
20歳未満の未成年者専用のNISA口座の開設が可能に
(2)NISAの非課税枠の拡充
取得対価の額の合計額の上限を年間120万円に引き上げ
(3)住宅ローン減税の適用期限の延長
適用期限を1年6ヶ月延長する
(4)出国時課税制度の新設
出国時に未実現のキャピタルゲインに対して課税される
(5)確定拠出年金の見直し
企業年金加入者、公務員、被扶養配偶者も加入対象に
(6)ふるさと納税ワンストップ特例制度の新設と特例控除額の限度額の引上げ
確定申告不要者は簡素な手続きで適用が可能になり、特例控除の控除限度額は所得割額の2割に引上げ
20歳未満の未成年者専用のNISA口座の開設が可能に
(2)NISAの非課税枠の拡充
取得対価の額の合計額の上限を年間120万円に引き上げ
(3)住宅ローン減税の適用期限の延長
適用期限を1年6ヶ月延長する
(4)出国時課税制度の新設
出国時に未実現のキャピタルゲインに対して課税される
(5)確定拠出年金の見直し
企業年金加入者、公務員、被扶養配偶者も加入対象に
(6)ふるさと納税ワンストップ特例制度の新設と特例控除額の限度額の引上げ
確定申告不要者は簡素な手続きで適用が可能になり、特例控除の控除限度額は所得割額の2割に引上げ
住宅借入金など特別控除の適用を受けるための要件はなにがありますか?
(1)取得または増改築などをした日から6ヶ月以内に居住すること
(2)住宅の床面積が50m2以上で取得または増改築後の家屋の床面積の1/2以上が居住用であること
(3)借入金は償還期間が10年以上(一定のバリアフリー改修工事及び省エネ改修工事の場合は5年以上)であること
(4)中古住宅の場合、築後20年以内(耐火建築物の場合25年以内)であること、
または昭和56年の建築基準法施工令の新耐震基準に適合するものであること
(5)増改築の場合、その費用が100万円(一定のバリアフリー改修工事及び省エネ改修工事の場合は30万円)を超えること
(7)居住用財産を譲渡した場合の特例(3,000万円特別控除・軽減税率・買換など)を受けていないこと
(注)申告に必要な添付書類
1.借入金の年末残高証明書
2.住民票の写し
3.家屋・土地の登記事項証明書
4.売買契約書、建築工事請負契約書などの写し
5.建築確認通知書の写しまたは増改築工事証明書
6.サラリーマンの場合は、給与所得の源泉徴収票
(2)住宅の床面積が50m2以上で取得または増改築後の家屋の床面積の1/2以上が居住用であること
(3)借入金は償還期間が10年以上(一定のバリアフリー改修工事及び省エネ改修工事の場合は5年以上)であること
(4)中古住宅の場合、築後20年以内(耐火建築物の場合25年以内)であること、
または昭和56年の建築基準法施工令の新耐震基準に適合するものであること
(5)増改築の場合、その費用が100万円(一定のバリアフリー改修工事及び省エネ改修工事の場合は30万円)を超えること
(7)居住用財産を譲渡した場合の特例(3,000万円特別控除・軽減税率・買換など)を受けていないこと
(注)申告に必要な添付書類
1.借入金の年末残高証明書
2.住民票の写し
3.家屋・土地の登記事項証明書
4.売買契約書、建築工事請負契約書などの写し
5.建築確認通知書の写しまたは増改築工事証明書
6.サラリーマンの場合は、給与所得の源泉徴収票
相続
来年から相続情報を紙一枚にする新制度
相続の法的手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」が来年スタートします。現在は相続の際に大量の戸籍書類一式をそろえて各自治体の法務局や金融機関ごとに提出しなければなりませんが、これからは相続人全員分の本籍や続柄、法定相続分などの情報をそろえて一度法務局に提出すれば、発行される証明書の写しを提出することで事足りるようになるのです。
親や配偶者が死亡した場合、相続人は不動産登記の変更や相続税の申告、銀行口座の解約などの手続きのため、大量の戸籍書類一式を管轄する各法務局や預金のある金融機関ごとに提出する必要があります。また、提出を受けた法務局や金融機関も、申請者が正当な相続人であるかを審査し、さらに遺産が多岐にわたるときは同様の手続きを複数の法務局や金融機関が行なわなければなりません。
新制度ではまず、相続が発生すると相続人の一人が全員分の本籍、住所、生年月日、続き柄、法定相続分などを記した相続人一覧をつくり、相続人全員分の現在の戸籍と、死んだ人の出生から死亡までの戸籍をそろえて法務局に提出します。法務局が正当な相続人であるかを審査した後、提出を受けた相続人一覧を基にして証明書を完成させ、公的な証明書として法務局が保管し、写しを発行。これによって相続人は、相続手続きを行う法務局や金融機関に証明書を提出するだけでよくなり、利便性が向上することを法務省は強調しています。
従来は煩雑な手続きがハードルとなって点在する不動産の名義人を変えないままにしていることが多かったのですが、手続きを簡素化することで政府は円滑な登記変更を促したい狙いです。 <情報提供:エヌピー通信社>
親や配偶者が死亡した場合、相続人は不動産登記の変更や相続税の申告、銀行口座の解約などの手続きのため、大量の戸籍書類一式を管轄する各法務局や預金のある金融機関ごとに提出する必要があります。また、提出を受けた法務局や金融機関も、申請者が正当な相続人であるかを審査し、さらに遺産が多岐にわたるときは同様の手続きを複数の法務局や金融機関が行なわなければなりません。
新制度ではまず、相続が発生すると相続人の一人が全員分の本籍、住所、生年月日、続き柄、法定相続分などを記した相続人一覧をつくり、相続人全員分の現在の戸籍と、死んだ人の出生から死亡までの戸籍をそろえて法務局に提出します。法務局が正当な相続人であるかを審査した後、提出を受けた相続人一覧を基にして証明書を完成させ、公的な証明書として法務局が保管し、写しを発行。これによって相続人は、相続手続きを行う法務局や金融機関に証明書を提出するだけでよくなり、利便性が向上することを法務省は強調しています。
従来は煩雑な手続きがハードルとなって点在する不動産の名義人を変えないままにしていることが多かったのですが、手続きを簡素化することで政府は円滑な登記変更を促したい狙いです。 <情報提供:エヌピー通信社>
平成27年度税制改正(相続税・贈与税)はどのようなものですか?
(1)住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充等
契約の締結日によって非課税限度額を決め、最大3000万円に拡充
(2)結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の新設
子や孫などへの結婚・子育て資金の贈与は、非課税
(3)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長等
使途に通学定期券代、留学渡航費等を追加
(4)事業承継税制の見直し
2代目から3代目へ株式等の贈与した場合に、一定の要件の下、猶予税額の納税義務が免除される
契約の締結日によって非課税限度額を決め、最大3000万円に拡充
(2)結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の新設
子や孫などへの結婚・子育て資金の贈与は、非課税
(3)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長等
使途に通学定期券代、留学渡航費等を追加
(4)事業承継税制の見直し
2代目から3代目へ株式等の贈与した場合に、一定の要件の下、猶予税額の納税義務が免除される
相続放棄した場合に受け取った保険金の課税関係はどうなりますか?
相続放棄は、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、
相続についてはじめから相続人ではなかったものとみなされる制度です。
相続放棄により、借金などマイナスの財産は引き継ぐ必要はなくなりますが、同時にプラスの財産も相続できなくなるので、
慎重な判断が必要です。
相続放棄した場合でも、自分が受取人となっている生命保険金は受け取ることはできますが、この場合は相続ではなく遺贈となります。
遺贈により.取得した財産にも相続税が課税されます。
相続税の基礎控除や配偶者の相続税の軽減などは適用できますが、生命保険の非課税500万円×法定相続人数は摘要できません。
相続についてはじめから相続人ではなかったものとみなされる制度です。
相続放棄により、借金などマイナスの財産は引き継ぐ必要はなくなりますが、同時にプラスの財産も相続できなくなるので、
慎重な判断が必要です。
相続放棄した場合でも、自分が受取人となっている生命保険金は受け取ることはできますが、この場合は相続ではなく遺贈となります。
遺贈により.取得した財産にも相続税が課税されます。
相続税の基礎控除や配偶者の相続税の軽減などは適用できますが、生命保険の非課税500万円×法定相続人数は摘要できません。
2011年度の税制改正(相続.贈与関連)はどうなりますか?
(1)相続税の基礎控除が3,000万円+600万円×法定相続となります。
(2)死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の法定相続人について以下の者に限定されました。
未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者
(3)未成年者控除及び障害者控除の引上げ
未成年者控除10万円、障害者控除10万円、特別障害者控除20万円
(2)死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の法定相続人について以下の者に限定されました。
未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者
(3)未成年者控除及び障害者控除の引上げ
未成年者控除10万円、障害者控除10万円、特別障害者控除20万円
税理士個人でも相続問題が発生するのですか?
税理士本人でも年齢によって相続の問題が生じます。日本のよき歴史の家督相続が廃止され、個人主義の相続が適用されるため、税理士も不合理を大いに感じます。1945年間続けたことを戦争に負けて180度変更させられた。墓のこと、跡取りのこと、家のこと等、日本人に個人主義が合うのか、家族主義を取り戻さなければいけないのではないか
-
不動産売却
相続で取得した土地建物をすぐに売る場合、税金はどうなりますか?
やはり譲渡取得に対する税金がかかります。相続した土地や建物を相続税の申告期限後3年以内に売った場合は、
自身が納付した相続税額のうち、土地などに対する相続税額を、取得費に加算して控除することができます。
また、土地・建物の相続時の不動産投機費用や不動産取得税も、他の所得の必要経費となるものを除き、取得費とすることができます。
ただし、売却価額の5%を概算取得費として計算する場合は、相続時の登記費用などをその概算取得費に加えることはできません。
自身が納付した相続税額のうち、土地などに対する相続税額を、取得費に加算して控除することができます。
また、土地・建物の相続時の不動産投機費用や不動産取得税も、他の所得の必要経費となるものを除き、取得費とすることができます。
ただし、売却価額の5%を概算取得費として計算する場合は、相続時の登記費用などをその概算取得費に加えることはできません。
自宅を売却した場合、税金はどうなりますか?
自宅を売却した場合には、売却代金から自宅の購入費、譲渡費用(不動産仲介料など)を控除した利益(譲渡所得)が
3,000万円までは税金がかからない特例(居住用財産の3,000万円の特別控除)があります。
3,000万円までは税金がかからない特例(居住用財産の3,000万円の特別控除)があります。
固定資産を交換した場合に税金はかかりますか?
土地と土地、建物と建物のように同種の資産を等価で交換した場合は、次の条件に適合した場合には所得税はかかりません(申告は必要)
【交換特例の条件】
1.交換譲渡資産と交換取得資産が、固定資産であり、相互に同じ種類の資産であること。
2.それぞれの所有者がともに1年以上所有していた固定資産であり、相手が交換の目的で取得したものでないこと。
3.交換取得資産を交換譲渡資産の譲渡直前の用途と同じ用途に供すること。
4.交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、これらの時価のうち多い方の金額の20%以内であること。
【交換特例の条件】
1.交換譲渡資産と交換取得資産が、固定資産であり、相互に同じ種類の資産であること。
2.それぞれの所有者がともに1年以上所有していた固定資産であり、相手が交換の目的で取得したものでないこと。
3.交換取得資産を交換譲渡資産の譲渡直前の用途と同じ用途に供すること。
4.交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、これらの時価のうち多い方の金額の20%以内であること。
収用などのため国などに資産が買い取られた場合の特例は?
(1)代替特例
収用などで土地や家屋が買い取られ、受け取った補償金で代替資産を取得した場合、
補償金のうち代替資産の取得価額までの部分は譲渡がなかったものとされます。
(2)5,000万円の特別控除
代替の特例に代えて譲渡所得から5,000万円の特別控除をした残額に課税されます。
したがって、譲渡所得が5,000万円以下なら税金はかかりません。
収用などで土地や家屋が買い取られ、受け取った補償金で代替資産を取得した場合、
補償金のうち代替資産の取得価額までの部分は譲渡がなかったものとされます。
(2)5,000万円の特別控除
代替の特例に代えて譲渡所得から5,000万円の特別控除をした残額に課税されます。
したがって、譲渡所得が5,000万円以下なら税金はかかりません。
-
確定申告
所得税の確定申告って何ですか?どういう場合に必要なのですか?
日本の法令において所得税は、自分の所得の状況を最もよく知っている納税者が、自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し、
納税するという「申告納税制度」を採用しています。
多くの方は給与所得について年末調整をおこなっているため、確定申告の必要はありませんが、
自営業を営む個人(個人事業主)や年金生活者などは、収入や費用を自分で申告しなければなりません。
所得税の申告期間は、2月16日から3月15日までです。
※税務署は通常、土・日・祝日は閉庁しています。
納税するという「申告納税制度」を採用しています。
多くの方は給与所得について年末調整をおこなっているため、確定申告の必要はありませんが、
自営業を営む個人(個人事業主)や年金生活者などは、収入や費用を自分で申告しなければなりません。
所得税の申告期間は、2月16日から3月15日までです。
※税務署は通常、土・日・祝日は閉庁しています。
所得金額はどのように計算するのですか?
所得はその性質によって次の10種類に分かれ、それぞれの所得について、収入や必要経費の範囲
あるいは所得の計算方法などが定められています。
1.利子所得 2.配当所得 3.不動産所得 4.事業所得 5.給与所得
6.退職所得 7.山林所得 8.譲渡所得 9.一時所得 10.雑所得
計算方法の詳細については税理士へお尋ねください。
あるいは所得の計算方法などが定められています。
1.利子所得 2.配当所得 3.不動産所得 4.事業所得 5.給与所得
6.退職所得 7.山林所得 8.譲渡所得 9.一時所得 10.雑所得
計算方法の詳細については税理士へお尋ねください。
所得金額全てに課税されてしまうのですか?
課税所得金額は、その方の1月1日から12月31日までの1年間(年分といいます。)の全ての所得から所得控除額を差し引いて算出します。
所得控除とは、扶養家族が何人いるかなどの個人的な事情を加味して税負担を調整するものです。
所得控除の種類や控除額についての詳細は税理士へお尋ねください。
所得控除とは、扶養家族が何人いるかなどの個人的な事情を加味して税負担を調整するものです。
所得控除の種類や控除額についての詳細は税理士へお尋ねください。
課税所得金額の何%が課税されるのですか?
所得税額は、課税所得金額に税率を適用して計算します。
【超過累積税率】
税率は、所得が多くなるにしたがって段階的に高くなり、
納税者がその支払い能力に応じて公平に税を負担する仕組みとなっております。
・195万円以下=5%
・195万円を超え 330万円以下=10%
・330万円を超え 695万円以下=20%
・695万円を超え 900万円以下=23%
・900万円を超え 1,800万円以下=33%
・1,800万円超=40%
【超過累積税率】
税率は、所得が多くなるにしたがって段階的に高くなり、
納税者がその支払い能力に応じて公平に税を負担する仕組みとなっております。
・195万円以下=5%
・195万円を超え 330万円以下=10%
・330万円を超え 695万円以下=20%
・695万円を超え 900万円以下=23%
・900万円を超え 1,800万円以下=33%
・1,800万円超=40%
青色申告って何ですか?
一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、
所得の計算などについて有利な取り扱いが受けられる制度です。
■ 青色申告をすることができるのは、事業所得のある方です。
■ 青色申告をしようとする方は、その年の3月15日までに「青色申告承認書」を税務署に提出してください。
※その年の1月16日以後に新たに開業した方は、開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。
青色申告には、以下のような特典があります。
・青色申告特別控除
・青色事業専従者必要経費算入
・純損失の繰越しと繰戻し
詳細は税理士へお尋ねください。
所得の計算などについて有利な取り扱いが受けられる制度です。
■ 青色申告をすることができるのは、事業所得のある方です。
■ 青色申告をしようとする方は、その年の3月15日までに「青色申告承認書」を税務署に提出してください。
※その年の1月16日以後に新たに開業した方は、開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。
青色申告には、以下のような特典があります。
・青色申告特別控除
・青色事業専従者必要経費算入
・純損失の繰越しと繰戻し
詳細は税理士へお尋ねください。
e-Taxって何ですか?電子証明書だとか難しそうですが…。
日本の国税に関する国営オンラインサービスシステムの呼称です。
正式名称を国税電子申告・納税システムといい、税金の申告及び納税に利用します。
e-Taxを利用して申告する場合、電子証明書の取得が必要になりますが、税理士が納税者の依頼で代理送信する場合、
納税者本人の電子証明書は不要となります。
詳細は税理士へご相談ください。
正式名称を国税電子申告・納税システムといい、税金の申告及び納税に利用します。
e-Taxを利用して申告する場合、電子証明書の取得が必要になりますが、税理士が納税者の依頼で代理送信する場合、
納税者本人の電子証明書は不要となります。
詳細は税理士へご相談ください。